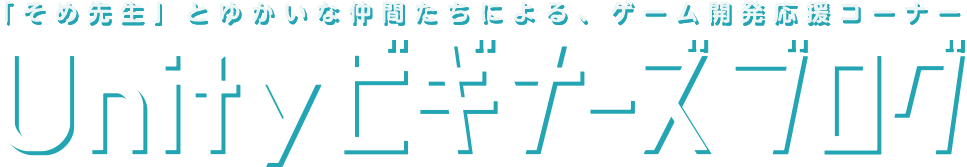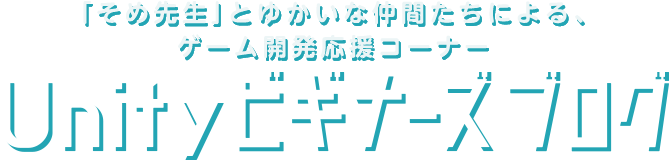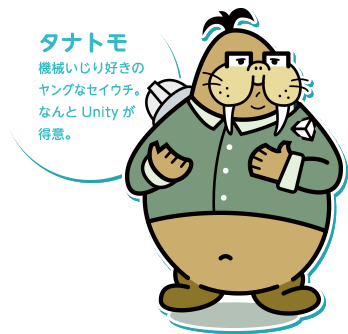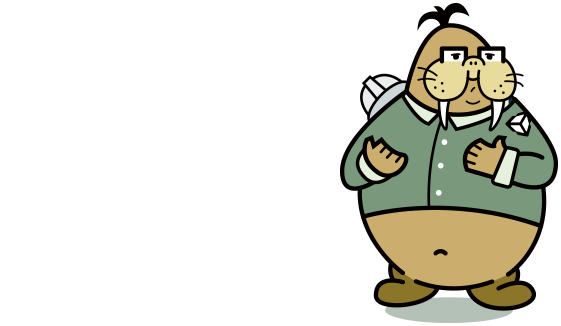自分のゲームを一言で説明してみよう
今回はゲームを企画するための
極意を語るぞ
極意を語るぞ
極意っすか!?
結論から言うと
「自分のゲームを
一言で説明できるようになれ!」
「自分のゲームを
一言で説明できるようになれ!」
えっ
そんなんでいいんすか?
意外と簡単そう……
そんなんでいいんすか?
意外と簡単そう……
自分の考えたゲームを一言で説明できるだろうか?もし説明が長くなってしまったり、うまく言葉にできないとしたら、そのゲームのどこが面白いのかを自分自身で認識できていないのかもしれない。
日本語というのは結構難しい。日本語なんていつも使ってるわけだが、ほとんどの人は日常会話やテストの回答、あるいはTwitterでのつぶやきくらいにしか使っていない。日本語が簡単だと思うなら「人の心をときめかせるようなラブレター」を140字以内で書いてみるがよい。そめ先生は書けん!
物事を短く、簡潔に説明するのは「主となる要素を抜き出す力」「わかりやすい言葉でまとめる力」が必要となる。今回は例題を出そう。ゲームの「ポケットモンスター」「パズル&ドラゴンズ」がどんなゲームなのか一言で説明してみてくれ(そめ先生の考えた答えは下に書くが、いったん自分でやってみよう)。
たにっこ君 30秒以内にやってみて
エエッ 30秒っすか!?
うーーーん……
うーーーん……
たにっこの答え
………。
エヘヘ……
自己採点で60点くらいっすかね……
自己採点で60点くらいっすかね……
喝ぁーーーッ!!!
ヒッ!?
そめ先生の答え
な、なるほど
こういう風に説明すれば良かったんすね
こういう風に説明すれば良かったんすね
まあ異論はあるだろうけど
筋は通ってると思う
筋は通ってると思う
■モンスターを捕まえてワザを覚えさせ、友達と交換して戦わせるゲーム
■同じ色のブロックを3色つなげて消していくモンスターバトルゲーム
……という事を
簡潔に説明したつもりだ
簡潔に説明したつもりだ
はぇー すっごい
色々考えてるんすね
でもこれが何の役に立つんすか?
色々考えてるんすね
でもこれが何の役に立つんすか?
例えば「育成RPG」を
作ろうとするやろ?
作ろうとするやろ?
は、はい
どんな育成で何をするゲームなのか、
何がおもしろい部分なのか、
理解できていないのではないか?
何がおもしろい部分なのか、
理解できていないのではないか?
うっ!
自分は果たしてどんなゲームを作りたいのか
ゲームを作り始める前に、それがどんなゲームなのかを紙に書き出して、家族や友達、あるいは頭の中のもう一人の自分に説明してみよう。最初の1ページ目にはゲームのタイトルを書くとしたら、2ページ目には何を書くだろうか?対応プラットフォーム?ゲーム中の画面?プロローグとなる世界観?主人公の名前と設定?操作説明?いいや違う、最初に書かなくてはならないのは「どんなゲームなのか」ということだ。自分はこういうゲームを作ろうとしている!ということを認識しなくてはならない。
モンスターを捕まえてワザを覚えさせ、友達と交換して戦わせるゲームを作る!となったら、モンスターの種類やデザインを考えたり、どんなワザがあってどうやってワザを覚えさせるか、友達と交換することのメリット、戦わせ方、などなど、骨組みに肉が付いていくように、色々な要素を自然と足していけるはずだ。
「育成RPG」じゃ
何から考えていいか
わからないっすね……
何から考えていいか
わからないっすね……
どんなゲームなのかうまく説明ができないということは、内なる自分に「とにかく爽快で面白いゲームを作れ」と言われているようなもので、それができねーから悩んでるんだろ!と頭の中でバトルが始まってしまう。
アイデアは何を書いてもいい。キャラクター、世界観、ストーリー、画面の説明。しかし、それだけではゲームを作れないのだ。そのまま作り始めたら、ただキャラクターが出てきて、動き回るだけのゲームになってしまうかもしれない。
実はボク 社会に出てから
こういうのニガテということに
気づいたっす……
こういうのニガテということに
気づいたっす……
社会に出ると
ゲームに限らず色々な場面で
必要になる能力だと思うんだよね~
ゲームに限らず色々な場面で
必要になる能力だと思うんだよね~
資料やレポート作ったり、
商品をお客さんに説明するときも
必要になるっすね
商品をお客さんに説明するときも
必要になるっすね
「○○が○○するゲーム」
というアイデアを
100個くらい書いてみると
コツがつかめるかもしれん
というアイデアを
100個くらい書いてみると
コツがつかめるかもしれん
これにもコツがある。ゲームというのはバトルとか育成とか買い物とかパワーアップとか色々な要素があるので、ついつい色々なことを説明しようとしてしまいがちだが、実は違う。重要でない要素を、説明から省くことを意識したほうが、説明は綺麗になると思う。
骨格に肉が付いたのが完成したゲームなら、肉を削ぎ落として、最後に残る「これだけは外せない要素」が何なのか。それこそがそのゲームの骨格、他のゲームと一線を画すオリジナリティのはずだ。
ゲームのハコの裏に書いてある
説明とか参考になるぞ
説明とか参考になるぞ
ハコの裏に
そんな重大な秘密が……!?
そんな重大な秘密が……!?
ゲームだけじゃなく
本や映画のあらすじとか
キャッチコピー、ストーリー説明も
観察してみるといいかもなぁ
本や映画のあらすじとか
キャッチコピー、ストーリー説明も
観察してみるといいかもなぁ
もうひとつ、ゲームの企画・内容を考える上で大切なポイントがある。「そのゲームをプレイして、どこが一番おもしろい瞬間なのか」を強く意識しよう。
クリエイターの田尻智氏が初代ポケモンを企画したときの根っこにあった骨格、発想の源は「ポケモンを交換する」ことだったそうである。交換するということは当然ポケモンに種類がある。ポケモン同士をバトルさせるから属性の相性(炎は草に強い、草は水に強い、水は炎に強い…)がある。ワザがある。どこにでもいるポケモンもいればレアなポケモンもいる。それらを探索して捕まえる世界がある。そんな世界では強いポケモンを使う集団や世界征服を企む悪の組織がいる。1人では攻略できなくても、友達が知らないポケモンを持っていれば交換できる。
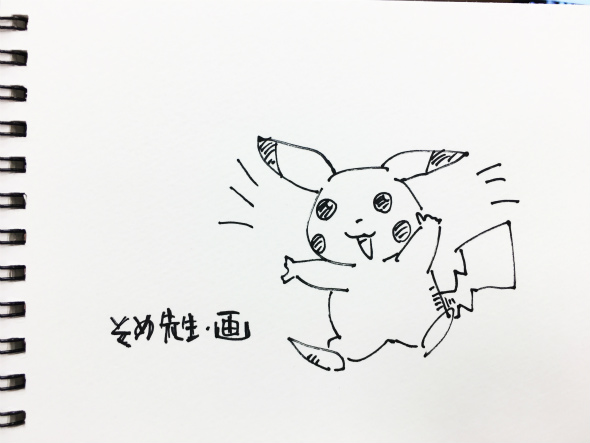
「交換する」ゲーム、ポケモン
と、まあ半分はそめ先生の勝手な考えだけど、一番おもしろい瞬間が決まれば、それを活かすためにどうすればいいか、方向性を持ってアイデアを考えることができる。無からアイデアは生まれない。自分のゲームを一言で説明して、一番おもしろい瞬間がどこなのかを認識してみよう。「そこ」さえおもしろくできれば、完璧ではなくとも「おもしろいゲーム」になるはずだ!
次回はそめ先生が大学生と一緒に作ったゲーム「せつぶんくん」を元に、初心者向けのゲームキャラクター作りの説明をしようと思います。